

|
| サイトリスト | ||||
|
古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |
京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリアの町並 アフガニスタンの町並 |
| 11 鞍馬寺から貴船神社へ | 11 鞍馬寺から貴船神社へ・スケッチギャラリーへ | おすすめサイト | ||||||
 |
 |
|
||||||
| 鞍馬寺三門 | 貴船神社 | |||||||
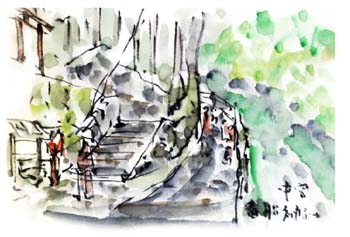 |
 |
|||||||
| 貴船 中宮 | 木の根道 | |||||||
| 京都インデックス | ||||||||
|
||||||||
| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||
| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |
||||||||
|
十一 鞍馬寺から貴船神社へ
鞍馬、貴船には学生時代にも訪れたことはなかった。鞍馬という妖しげで武骨な語感の響きに、一度は訪ねてみたいと思っていた土地であった。何よりも源義経が幼少牛若丸の頃過ごした鞍馬寺がある地だから。
まだ小学生の頃、漫画で牛若丸の活躍は見知っていた。牛若丸が鞍馬から一人、如何にも女装といった出で立ちで薄衣を身にまとい五条大橋を笛を吹きながら歩き、武蔵坊弁慶に見(まみ)えた光景を漫画ながら、胸躍る思いで読み耽ったことを思い出す。
弁慶の長刀をヒラリと躱(かわ)し、五条大橋の欄干にふわり(・・・)と舞い上がる姿に、自からの分身であるかの如く、羨望の眼で見たのを憶えている。
叡山電鉄を鞍馬に向かって進むに連れ、牛若丸の時代、平安時代末期千数百年の昔にタイムスリップして行くのを感ずるのであった。
叡山電鉄出町柳駅は終着駅のつくりである。改札口を抜けると、横に永く伸びたホールから、竪に二本のプラットホームが伸びる。其処には既に二両連結の可愛らしい車両が停まっていた。吊革に?まる探索者はいないが、思ったより座席は混んでいる。車両を見渡すと年寄りが多い。
出町柳なる地名は何も知らなければ、由緒ある柳の並木がありそうな名である。学生時代より其の地名だけは知っていた。更に昨秋、守本氏と待ち合わせた駅でもあるので身近に感じていた地名である。
車窓には若葉に包まれて風情のある民家が連なり、穏やかな光景が流れてゆく。
宝ヶ池を過ぎた辺で、比叡山が間近に迫まる。頂上に人工的な施設が白く輝くのが遠望でき、比叡山であると直に分かる。
比叡の山並は南北に連なり、北に向かうに従い、低くなって遠ざかり薄紫色に霞んでゆく。山並が複雑に絡み合う山の懐に抱かれ、何とも云えない平和な気分だ。
宝ヶ池は懐かしい処だ。かつて訪れたことのある円通寺が近くにある筈だ。円通寺の苔生した庭園は比叡山を借景にしている。庭は低い垣根で囲まれ、垣根の外には巨樹が数本立ち上がり、樹幹越しに遥か彼方に比叡山が薄紫色に霞んでいた。
広縁に立ち、墨染めの衣に身を包んだ背が高く、背筋のシャキッとした和尚さんが微笑を浮かべ得意そうに、比叡山借景の件を説明して呉れた事を懐かしく思い出した。
孰(いず)れは円通寺を訪れようと思いながら、今だに再訪していない。市内に比べ、交通の便が悪いためか、他に探索せねばならぬ処が多いためか・・・。
其んな昔日を思いながら、車窓に流れる比叡連山を眺めていた。新緑の芽吹きの鮮かな若葉が連なり、車窓に流れる景色は素晴らしい光景であった。
処々、薄いピンク色の花を咲かせた八重桜が、人家の庭先に重たげに頭を垂れ、ピンク色の躑躅(つつじ)がポツンポツンと咲くのが見える。
近景にある楓の新緑の若葉は萌黄色の鮮かな彩を現し、少年のような初々しい姿を見せている。一方、杉の濃緑の葉は、壮年から老年への時を刻んでいるかのような落着きを見せ、風に揺れていた。
鞍馬に近付くに連れ、車窓の下を流れる鞍馬川沿いに発展した集落の家並の瓦屋根が、銀鼠色に反射し、眩(まぶ)しい程の輝きを放っていた。
もう少し古い集落かと期待していたが、意外と新しい印象の家並である。一見、家自体は古いのではと思うが・・・。
リニアーに連なる民家が新緑の海に浮かぶ様に、こんな処で住めたならば、どんなにか素晴らしいのでは・・・。車窓に山が近付き、木々の若葉一枚一枚が山麓に流れる風に戦(そよ)ぐのが分かりそうな程、穏やかな風景である。
鞍馬駅前広場には土産物店が立ち並び、坂になった広場下方の道路に口を開いていた。探索者の群れは自然に、其方に流れ降ってゆく。
道路を出た左方に、かなり高い石段の頂に朱色の楼門が小さく見える。鞍馬寺仁王門だ。仁王門への石段は大きく三段に別れ、先方になるに従い巾は狭くなり、石段の両脇には新緑の若葉が差し掛かり、仁王門が若葉の海に浮かんでいるような光景である。
遠方から望む仁王門の朱色は、かなり煤(くす)んで見えるが、それが又、閑雅な佇でいゝ。近付いて仁王門を見上げた。遠方から眺めた際に感じた程、朱色は煤んでいない。周りの若葉に溶け込んでしまったのかも知れない。
石段下の駐車場脇で仁王門を描き始めた。私が描いている道路の対面は食堂であった。食堂の内部は暗く、幾人かの人影が見えた。誰にも見られずに描いていると思ったら、食堂から此方を見ている気配を感じた。
処々に燈籠が置かれた石段の左方には坂道が伸び、若葉に包まれて旅館風の建物が立つ。後で鞍馬寺の栞を見たところ、これは旅館ではなく、鞍馬寺の修養道場であることが分かった。
石段には中間に踊場が二段あり、其処から石段巾が狭まるので、実体より遠近感が強調され、仁王門に吸い込まれて行きそうな錯覚を憶える。
仁王門は背に緑葉を控え、藍青色の空にくっきりと浮かぶ。山腹に立つ仁王門だけに流動的で変化あるアプローチ空間を構成しているのであった。
石段を登り、徐々に仁王門に近付く。近付くに従い、惚れ惚れする素晴らしい山門が姿を現し、石段中間あたりでは、仁王門は広々とその翼を拡げ参詣する者を迎えるのであった。
見上げる仁王門は迫力があり、今にも動き出しそうに生き生きと迫って来る。因みに仁王門両脇には、仁王像が安置されてある。
三門両脇に仁王像を安置するので仁王門と云う。仁王像を据える事が様式化され、規範に則って建てられたのだろうが、民衆が潜る門の両脇に仁王像を安置し、山内に歩を入れる民衆を仁王像が見据える構図である。山内に入る民衆の邪念を払いのける演出を建築的に空間化している。この空間化を始めて計画した匠の奇想天外な発想には、何処の山門を見ても感心させられる形である。
何気なく眺めている際には、わっ凄いなあと思うだけだが、其処に仁王門がまだ立っていない白紙の空間を考えた時、昔人の匠の造詣力の豊かさを想う。
このまゝ仁王門を潜って鞍馬寺境内を彼方此方見て歩き、木の根道を通って貴船に抜けて行く積もりだ。鞍馬には戻らないため、仁王門を潜る前に若狭街道沿いの街並を見ていかねばならぬ。
鞍馬寺仁王門への石段を進む手前の角を折れて若狭街道が伸びる。其方の道に歩を入れた。真直に伸びた道は、左方に大きく弧を描き、古い家並、そして背後の緑に包まれた山並の谷筋に吸い込まれて行く。
朝早いせいか探索者の姿はまだ見えない。恰も死んだ街並を思わせる佇だ。両脇には古い佇を残した民家が連なり、古くからの若狭街道の面影を思い起こさせる。旧家のひとつ、瀧沢家<匠斎庵(しょうさいあん)>は見学できることは前以て調べておいた。
街並を描いている間に、由緒ありそうな家の前に車が止まり、車から若い女性が降りて大きな板戸を引き、内に消えて行った。
描き上げ、由緒ある家の前に立つ。女性が消えて行った戸は大きな框戸の引戸である。四周の框の中は細かく格子が組まれ重厚な板戸だ。脇の立札に―匠斎庵―と掲げられてあるが、時間が早いためか、戸を引いても内側から閂が差され開かない。
暫く道の対面に立ち眺める。家の妻面の両脇には、妻面を隠すように<?>(うだつ)が設けられ白く漆喰が塗られてある。?の頂には瓦がのせられ、両脇の家との境界が判然としているのである。
家をつくる際、この?を立ち上げる事は、江戸期、家の主の身代(しんだい)を現す事に繋がっていた。それは機能的には、連続的に連なる町家において、防火上の意味があった。?は通常、屋根面より突き出し、かつ壁面からも出端らせて造られた。隣家火災の際には、火が隣接地に延焼しないようにするために設けられたのである。
延焼を免れるための重要な要素だった訳である。?を立ち上げる事は当時の男としては当然の責任であった。それには経済的負担を強いられる。それが出来ない男を称して―?の上がらぬ男―と云われた。
そろそろ開く頃だろう、大きな板戸の竪框に手を掛け引いた。大きい割に思ったよりスムーズに板戸は横に滑った。入って直に竃のある土間が正面の庭まで続く。土間の右手に三間続きの座敷がある。複雑で盛り沢山の要素を持った小庭からの光が眩しく感じられる。
二階に隠し部屋があると云う。<ざしき>の片隅に据えられた箱階段で上がるのだが、天井があり入れない。開店準備中で、忙しそうに動き回る女性に二階に上がれない旨を話すと、直に階段部の天井を滑らせて呉れた。
箱階段を恐る恐る上がると、其処は六帖間程の小さな座敷で天井高は低く二メートルそこそこだ。塗壁の片隅に踏込床(ふみこみどこ)風に床の間があり、掛軸が吊され、床(とこ)にはさりげなく花が活けられてあった。書斎にしたら落着きそうな空間だ。
江戸中期、二階建ての町家は禁じられていたので、外からは平屋に見えるように建てられたため天井高も低く押さえられたらしい。
庭に面する<おもて>には、黒光りのする床、違棚、佛壇が据えられてある。ざしきから、縁、小庭へと流れるような流動的な空間が醸し出されている。お茶を飲みながら小庭を描く。
匠斎庵の栞によれば、庭の背後の山腹には三段の石垣が積まれてあるらしいが、此処からでは緑葉で包まれ判然としない。何処から水が流れこむのか庭園中央に小池がある。流れに差し掛けられた石橋、燈籠、手水鉢そして池畔に据えられた岩が池の周りに配されてある。 池際の四季の草花が風に揺れ、池から離れて程好い高さの木が立ち上がる。外縁とは新緑の若葉で結界が築かれ、町家の庭にしては濃密な空間だ。
帰り掛け、準備に忙しそうに動き回っている女性が、
「絵を描いているんですか、少し見せて下さい」
と話し掛けられ、再び<おもて>の座敷に上がり、スケッチブックを開いた。そのうち奥方から年配の女性も出て来、一緒にスケッチを見るのであった。スケッチブックを開きながら、鞍馬の歴史について訊ねる。
「鞍馬は若狭と京洛中との中継地として古くから栄えた。炭の生産地としての役目もあったが、それもほんの僅かになりました。木の芽漬が今では有名です」
「そうですか、こんな山奥で皆さん何をして生計を立てているのかと思いました。市内に比べ、鞍馬は随分寒いですね」
「町より四度低いので、町での恰好では寒いですよ」
瀧沢家住宅はどうして、匠斎庵なる名称なのか訊ねた。
「この辺では、名前を屋号で呼ぶんです。匠斎庵は屋号なんです」
と見る程でもない絵を見ながら話して呉れた。
鞍馬寺仁王門を潜れば、真直に参道が伸びるか、小広場でもあるのかと無意識に思っていた。ところが仁王門を潜った処は狭い空間で、直に右方に折れ、石段が幾段も続く。石段はかなり高くまで伸び、頂近辺には陽が差し一際、明るく輝くのである。
巾の狭い石段の両脇には、朱色に塗られた燈籠が一列に連なっていた。鞍馬寺参道と云うより、神社の参道のような空間であった。
江戸時代以前は寺と神社とはひとつの境内に混合して存在していたが、明治時代の神仏分離政策により寺と神社が分離されたのである。
鞍馬寺においても由岐(ゆき)神社がある。天慶三年(九四〇)鞍馬寺が御所から鎮守社として勧進した神社である。そんな歴史的背景があって、燈籠がある訳だ。かつて大寺院だった寺では鎮守社として神社を附帯していた。奈良県境当尾の里にある岩船寺でも境内に鎮守社として白山神社を持っていた。当然の事ながら、現在では別の宗教法人として存在している。
敷地条件により、参道のとり方が、マニュアル通りでないところが意外性があって面白い。
室生寺でも似た手法が見られた。室生川に掛かる朱色の太鼓橋を渡り、右手に折れ室生川沿いに伸びて参道があった。
石段の頂では広い砂利道が上に伸び、砂利道に沿って右手にも小さな祠の間を抜ける道があった。
そのひとつ魔王の滝は豪快で迫力がある。木立ちが立ち上がる幽暗な崖上に、小さな朱色の祠があり、そこから突き出た石の水路から、山からの水が流れ落ちる。下方の剥き出した岩肌、処々、岩にへばり付いた若葉、固い岩から突き出た巨樹の樹幹、それらは、流れ落ちる一筋の水の糸のための空間装置である。ひとつひとつの要素はスケールが小さいが、描いた絵を眺めると、相当に大きなスケールかと錯覚してしまう。幽暗な祠周辺であるが、手前は新緑の若葉で包まれ、陽を浴びて輝く。その対比は素晴らしい光景だ。
再び、広い砂利道に出る。坂道の正面に石鳥居が見え、直背後に舞台造の建物が控える光景が眼に飛び込んできた。由岐(ゆき)神社の割拝殿だ。石鳥居と殿舎が接近してあるので、自然あふれる山内では異和感がある眺めであった。
異和感と云うより、鳥居の材質である石にもよるのだろうが、頑固一徹な豪気さが窺える。 石鳥居を潜る。割拝殿の中央部が刳(えぐ)られ境内に上がる石段が付けられていた。鳥居から境内地へはかなりレベル差がある。割拝殿には高いレベルにある境内から入る。そのためレベル差分だけ、清水寺舞台の如く、柱、梁で構成された舞台造になっている。それが小さいながら豪快な印象を与えるのであった。
画像でしか見た事がないが、鞍馬の火祭はこの由岐神社の例祭で、毎年十月二十二日の夜半
に行われる。豪快な鞍馬の火祭の光景と、今眼前にある割拝殿の印象がピタッと重なる。この頑固一徹な空間ありて火祭あり・・・。
石段の頂は由岐神社の境内だ。正面に本殿、左手に社務所がある。
由岐神社から鞍馬寺本堂までの参道は道巾は広目でよく整備されている。曲がりくねった―九十九折り―と呼ばれる石段を登り本堂前広場に至る。
本堂周辺は、今までの幽暗な野趣溢れる空間と異なり、底抜けに明るく景観の好い処だ。
正面中央に朱色の本堂が立つ。広場には八重桜のピンクの花が鮮かに咲き乱れ、広場一面に砂利が敷詰められてあるが、肌理細かさが感じられず大味な空間だ。 仁王門、魔王の滝のイメージを追い、更に幽暗な本堂を期待していたが、それには程遠い本堂である。
本堂の朱色に塗られた柱には質感が感じられない。その筈だ。木造の様式を鉄筋コンクリートに置き換えただけの本堂だからである。
牛若丸が過ごした頃の鞍馬とは程遠い本堂に違いない。せっせと先人の遺した歴史的遺産を食い潰している姿、生活しか見えない。昔人があの仁王門、魔王の滝、由岐神社を創り上げた豪快な気風は何処に行ったのか・・・。
広場周辺に据えられたテーブルを囲み昼食中の親子連れ、グループが大勢いる。安易な偽物空間から一刻も早く去りたい。
本堂左手の細道を奥院に進む。本堂までの参道と異なり、擦れ違うのがやっとと云った感じの山道だ。途々いくつかの堂があった。
細道の途次、一息するのに都合のよい小広場があった。其処には霊宝殿を中心に幾つか人工的施設があった。
与謝野晶子、鉄寛の歌碑が、緑葉に包まれて立つ石に刻まれてある。
何となく君にまたるるここちして いでし花野の夕月夜かな 晶子
遮那王が背くらべ石を山に見て わがこころなほ明日を待つかな 鉄寛
先方には、東京から移築された与謝野晶子の書斎冬柏亭(とうはくてい)がある。鞍馬寺と与謝野晶子、どんな関係があるのか。鞍馬寺宿坊にでも逗留したことがあるのだろうか。
杉の巨樹が林立する中を進み、奥院魔王殿に着く。鞍馬寺本堂から多くの探索者がこの奥院に来ていた。其処は木立ちに囲まれた陰気な空間で、魔王殿の他に二三祠があったような気がする。
奥の院と名の付く寺でその空間に感激した事はない。奥院と称するからには、本殿よりも奥床しく閑雅な空間があるのではと思うが、大抵は期待外れに終わることが多い。
ただ奥院に至る参道空間は何処でも素晴らしい。醍醐寺、室生寺の奥院への道もこの参道を歩かずして、醍醐寺、室生寺を語れないほどの素晴らしい空間であった。
まさかこの陰気な魔王殿が奥の院とは思わず、更に先方に奥院があるだろうと進む。直に地表に木の根がのた打ち回る異様な光景を現した広場、というより道がふくらんだところと云った方がよいかも知れない広い処に出た。
丁度昼どきで、巨樹が立ち上がる処々で、シートを拡げた大勢のグループがいた。ひとりで探索する姿は珍しいらしく、一斉に此方に視線を向けてきた。これが―木の根道―か・・・。
地図によれば、奥院の先方に木の根道がある筈だ。やはりあの陰気な魔王殿が奥院だったのか。
鞍馬山一帯は、海底火山の隆起によって変化ある地形が形成された。一帯は岩盤が固く、巨樹と云えども地中深く根をおろせず、地表に根を這わせているらしい。とは云えこれだけの巨樹が地表に現れた根だけでは、厳しい風雨に耐えられないだろう。
岩盤の割目を探し、地中深くに根を張っている筈である。根の一部が地表面に現れ、大蛇の如く、のた打ち回る奇観を為しているのである。
それは木の根と云うよりも、幹の延長、枝のような肌合いである。山を歩いていて、時々木の根が地表に現れた光景を眼にするが、これだけの群落は見た事がない。周りに探索者が大勢いるので奇観と一言で表現してしまうが、ひとり月光の下でこの空間に身を委せたならば、生き物の如く、養分を求めて触手を伸ばす木の根に、ゾッとするような妖気を感じるであろう。
木の根は、盛り上がり水平に伸び、半分地中に潜り再び顔を出す。他の根と絡み合い、上になったり下に潜ったりして複雑に触手を伸ばすのである。 眺めたところ、木の根が現れているのは、人間が歩く道だけだ。もともと地表近く這う根が、踏み荒らされ地表面に剥き出されたようにも見える。自然と人間が創り上げた光景かも知れない。
処々、樹幹と土が接する辺に緑葉が見られ、描く絵の好い点景になる。巨樹の林立する奥方に進む。そこには数人の探索者がいるだけだ。其処はさらに広い空間である。木の根は地表に現れているが、前処のような激しさはなく、地表面は黒く見え、まだ表土が被っている。その一角に安普請の小屋があった。小屋には何があったのか忘れてしまったが、壁は板が差し渡されただけの簡素なものであった。近辺には巨樹の樹幹が疎らに立ち上がり、今までのように妖気漂う空間ではなく、乾いた明るい印象の空間であった。
其処から貴船へ抜ける道を行く。人は殆ど見かけない。人がいないと不安になるが直に木の根道本道に出た。
貴船までの木の根道には、大勢の探索者が貴船神社を眼指す姿があった。カップル、子供連れはもとより、年寄りも数多く見掛けた。下り坂とは云え石段が多くあり、かなり厳しい道であった。
中間地点辺に、樹幹だか根だか見分けの付かない老木が、立つと云うより横たわっていると云った方がよいような巨樹があった。太く横たわる樹幹に、自からの根っ子と思われる根が蔦のように絡み付き、枯れているのか生きているのかさえ判然としない。若干緑葉を付けているので生きているのが分かる程度である。不思議な光景だ。下山中の探索者の誰もが立ち止まり、老木を背景に写真を撮る姿が見られた。
木の根道でこの光景が最も印象に残る光景であった。貴船までの木の根道は巨樹が林立する道であった筈であるが、今こうして原稿を書いていて、どのように巨樹が林立していたのかと思い出そうとしても頭にその光景が甦って来ない。
余りにも多くのものを見過ぎて、その時は素晴らしい光景であっても、老化した脳細胞のキャパシティーをオーバーしてしまったのか、自分でも分からない。杉の巨樹の林を歩いていた時には、凄い道だと感じていたのは確かであった。
印象を表現するには、再度木の根道を歩かねばならぬ。それは仁王門とて同じ事である。併し表現できなくとも、その素晴らしい空間のエッセンスは脳細胞の奥深くに閉じ込めてある積もりだ。
奥の院より三十分程で鞍馬寺西門のある貴船口に出た。西門にも拝観受付があり、幾人かの探索者が木の根道を登り奥の院を眼指しつつある。同じ道を再び鞍馬寺へ戻れと云われても、その気は起こらぬであろう。
西門より貴船川に差し掛かる橋を渡り対岸の道路を川沿いに登る。道の両側には料理旅館が立ち並ぶ。まだ貴船神社の朱色の鳥居は見えない。鳥居手前の川沿いに閑静な佇の料理旅館があった。
其の相互貫入された巧な空間構成に、思わず息を呑んだ。料理旅館は道路と貴船川に挟まれて立つ。旅館の反対側道路脇に、緋毛氈の敷かれた長椅子が置かれ、灰皿も用意されてある。長椅子に座り、木の根道登山に疲れた体を休め、一服した。
其の店は、向かって左手に玄関がある。正面には、道路より数段下がって格子戸が立てられ、奥方の川縁に抜けられる。幽かに川の流れが陽を受け光るのが見える。対岸に咲き乱れる若葉が爽やかな輝きを放ち、何処から何処までが私的空間なのか判然としない。
私が道路から降り川縁に行く事も出来る。強いて云えば格子戸が境界を現す装置に見える。石段を降る処には瑞々しい若葉を付けた低灌木が両脇に立ち上がり、右手には一際高い楓が紅色の葉を靡かせて立つ。灌木の周りは自然石で囲まれる。それらの補助的要素が建物を引き立てる名脇役を演ずるのであった。
降る石段の上部に太鼓橋風に橋が渡され、手摺も橋と同じく弧を描く。橋の床には丸太が敷き並べられ、その木口が円く外に現れ、閑静な佇の中に野趣豊かな趣きを現すのである。手摺を支える竪の手摺子が空間に緊張感を与える。
この太鼓橋の渡り廊下には、建具は嵌め込まれてなく吹晒しの空間である。描く間にも太鼓橋を着物姿の仲居さんが行き交う姿があった。その姿を見てこの太鼓橋が、左右の空間を連結する外部とも内部とも識れない空間であると分かった。始めはこの太鼓橋は、意匠的な飾りのバルコニーかと思っていた。
橋の巾は多分一.二メートル程だろう。奥の壁はベージュ色をした塗壁で、真壁の両脇に柱が静かにかつ穏やかに立つのである。壁下部には、横に長く板が打ち付けられ巾木風に見える。壁上部には―枕流亭―なる額がさりげなく掲げられてある。
橋には建具は建て込んでないが、屋根は葺き降りて来ており、風雨は避けられる。早春とは云え強い陽差しを受け、奥壁部に濃い影を落としている。庇先端両脇には、提灯が吊り下げられ、夜半には明かりが灯(とも)され風情のある光景が見られるに違いない。
料理旅館の名は―ふじや―と云う。空間構成の素晴らしさだけでなく、肌理細かいディテールを見、建築家として奮い立つ意欲が出て来るのであった。
私が描いている側に料理旅館ふじやの厨房裏方の建物があり、仲居さんが行ったり来たりする姿があった。描く間にふじやの女将が出て来た。狭い道で結構、車も行き交い、探索者も多く通るので、交通障害になるからと、注意されるのではと思ったが、そう云う訳でもない。
「素晴らしい空間ですね。こゝは旅館なんですか」
「ええ、料理旅館ですが、最近は不景気で、うちは高そうに見えるのか、客がようきはりまへん。よその店では客の呼込みもしてはるようですけど・・・」
門構えが立派で格式があるので、今風の経営をするのには抵抗があるようだ。それなら他店と同じようにすればよいと思うが、其れがなかなか難しく決断がつかない。
先を歩く者の苦しさである。私にも経験はある。武士は喰わねど高楊枝とでんと構え、来るものは拒まず、去るものは追わずの心境であろう。併し仲居さん、板前さんの給料もあって女将の苦労は大変な事だ。内情は分からぬが、女将が料理旅館を取り仕切って旦那さんは何をしているのか・・・。
料理旅館ふじやを描き上げ数歩進む。其処には、艶やかな彩を奏でる素晴らしい空間がはち切れん許りに展開するのであった。貴船神社へのアプローチ空間だ。アプローチ空間は何故、斯様に息を呑む空間なのか。鞍馬寺仁王門でもそうであった。寺、神社の顔だからか。そんな年増の厚化粧ではない。内部から湧き出る美しさが現れた空間だ。
鳥居なり山門で異質の空間に這入り込む境界を感じるからか。鳥居から一歩外に出れば、人間の思惑渦巻く現実世界だ。客が来なければ経営が成り立たぬ、先方の客に四時に会わねばならぬので脇目も触れず車で突っ走る、来月は奈良に支店を出すのでその資金繰りに銀行に行かねば・・・、支店長は誰にしようか、求人を出そうか・・・。
|
 |
 |
| 貴船 富士屋 | 鞍馬 魔王の滝 |
|
其んな忙しい現代人が、ある時ふっと時間の空白ができ、鳥居前に立ち静かに石段を上がる。そんな息抜き空間なのか。
日常的な現実界から非日常的な空間への変換装置として鳥居があり、石碑がある。変換の仕方が巧であると、来る人に感銘を与えずにはおかない。非日常的空間をつくる要素は、突然できた訳でなく、長い歴史の上に徐々に培わ(つちか)れて来たのである。一本の巨樹にしても、始めから巨樹であった訳ではない。
異質なものが重なり合う接点、日本の場合は接点と云うよりか接線のような気がする。更に大きな視野で見れば、異種文明の交じりあう接点にも素晴らしい文化が生まれる。例えばスペインにおけるイスラム文化とキリスト教文化。イスタンブールにおけるイスラム文化とキリスト教文化の混合がその一例であろう。
貴船神社の朱色の鳥居を眼前にして、余りの素晴らしさに其んな事を思い巡らすのであった。
右手に伸びる道に並列して大きな朱色の鳥居が立つ。脇に―貴船神社―と彫られた石碑が道路と結界を現す如く立つ。基壇の大きな石が腰掛けるのに都合の好い高さで、腰を下ろし休む探索者が二三人いた。
鳥居の門型の中を石段が左にカーブして登り、緑葉に溶け込んでゆく。石段両脇には朱色の燈籠が連なり、奥方で朱色が重なり合う壮観な眺だ。石段が登っていることにより遠近法が強調され、奥行の深い構図だ。
朱色の鳥居と石碑は、がっちりと大地にふんばって立つが、石段、燈籠は新緑の瑞々しい若葉に包まれ、緑海に浮かぶ如くある。描く間にも幾人もの探索者が石段を行き交うが、絵は写真と違い、不必要なものは消去でき都合がよい。
鳥居を潜り、石段に歩を進める。左にカーブした石段の頂に、貴船神社の小さな山門が口を開け、開かれた門に陽が差し明るく輝くのが見える。石段両脇に連なる朱色の燈籠が朱色だけに目立ち、石段の参道空間を支配するかのような燈籠の連なりである。
石段に差し掛かる楓の若葉が陽を受け輝く様には、水中から水面を見上げた時のように、キラキラ輝き光の戯れを感ずるのであった。
石段は左にカーブし、真直に小さな山門に至る。山門と云うより境内との境を現すだけの簡素な門である。貴船神社の境内地は二つのレベルに別れる。下の広場は崖に面し、其処には屋根の付いた見晴台がある。
既に数人の探索者が長椅子に腰掛け眼前に拡がる新緑の若葉を眼にし、疲れた体を休めていた。皆さん素晴らしい新緑に見蕩れ無言だ。
川向こうの楓の新緑が陽を受けて輝き、春の穏やかな風に靡いていた。見晴台から眺めるより、外に出てパノラマで遠望した方が気分がいゝ。
併し紅葉の季節には、多分席の取合いでこの見晴台は賑やかな事であろう。後でこの見晴台を崖下から見上げた。新緑の若葉に包まれた崖上に跳ね出して造られた見晴台は迫力があって新緑の好い点景に見えた。見晴台から眺めるより、見晴台を眺めた方がよっぽど好い光景だ。
門脇に御神木の桂の(かつら)木が立つ。根元から数十本の枝が樹幹の周りを取り囲んで立ち、凄い光景だ。 貴船は古くは気生根(きふね)と云われた。木は気の生ずる根元と言う意味の事が傍らの立札に書かれてあった。
何時も不思議に思うことがある。神社や寺には御神木と称して、斯様な珍しいそれこそ気を生じそうな巨樹が立つが、どうして都会にはそれが見当たらないのか。ただ単に開発のために伐採されてしまったのか、それとも元々、神社仏閣が立つ処には、霊が宿り気を生ずる根があったのだろうか。
桂の木の上方では主幹から横に長く山門にまで枝を差し伸べ、緑葉を付けている。一面に付けるのではなく、澄み渡った空が透けて見える程度の少ないものである。
御神木のある広場より、石段で僅か許り上がって、右手に本殿、左方に社務所がある小広場に至る。小さな境内を構成する要素、環境には惹かれるが、単体の人工的要素には心惹かれるものを感じない。
朱色の燈籠が連なる石段と反対側にある出口から、くねくねと曲がった石段で降りる。眼前に一面に拡がる薄い萌黄色をした楓の若葉が風に靡き、少年の清々しい姿を現すのである。
貴船川沿いを奥院への道を進む。川沿いに立つ料理旅館が管理する川床料理の仮設の川床が、流れを跨(また)いで川岸の岩と岩に架け渡されてある。川床には緋毛氈が敷かれ、四人用の卓が幾つか並べられてある。春とは云え此処貴船では、肌に流れる川風はまだ冷たく感じられる。幾人かは、その川床で川魚料理を愉しんでいる。風流な眺めだ。風流を解さない私などは、川が増水したら困るだろう、などと余計な心配をしてしまう。
道路の反対側にある店から仲居さんが、川岸まで伸びた階段を慣れた腰付きで行き交う。そんな光景を奥院への道を歩く探索者が見降ろしている。川床から見上げる若葉の戦(そよ)ぎも又格別の趣きがある光景であろう。
川床に設えられた床は店によって、少しづつ違った仕方である。川巾も処により僅か許り異なり変化がある。処によっては落差の少ない滝などもあり、上手に考えたものだと暫し見蕩れてしまった。
川床料理の店が途切れた辺の左手に、道に平行して緩い石段が登り、数段上がった林の中を左方に折れて登った頂に、朱色の可愛らしい鳥居が立つ。
朱色の鳥居を潜る。貴船神社中宮と石段下の説明書にあったが、小さな祠がある丈だ。潜った処はいくらか広く、林中を廻遊する道に面し、和泉式部の歌碑が立つ。
もの思へば沢の蛍も我が身より憧れいずる魂かとぞみる 和泉式部
おく山にたぎりて落つる滝つ瀬の玉ちるばかりものな思ひそ 返歌
歌碑に見入るカップルの女性が何やら述べた。私は和歌をよく解しないがカップルの女性は直に分かったらしく、
「・・・と云うんなら・・・しないでいいじゃん。難しく考え過ぎるよ」
才女なのかドライなのか、顔を拝すると頭脳明晰な顔付きである。男も返す言葉も見つからず微笑を浮かべるのみだ。「オッサンこんな事も分からへんのか」と云われそうで、早々に石段を降りた。
奥院への道にはカップルが多い。それもその筈だ。この道は通称―恋の道―と称されるのである。
和泉式部は夫の心変わりを悩み、この奥院への道を通り、貴船神社奥院に詣でた。当時は奥院に本殿があったらしい。そんな事から恋の道と云われる。
才女から逃(のが)れるように恋の道に歩を進める。左手木立ちの中、道に面し―相生の杉―が立つ。二本の杉の巨樹が大地から突き出ている。林中の他の樹木に比べ、相生の杉は太くて豪快である。一見二本に見えるが、根は一緒で、その部分は土と根が複雑に絡み合い、地面で盛り上がっている。 相生の杉も御神木であり、標縄がかけられ妖気が漂う。
川沿いの道に平行した遊歩道になった。境に杉木立ちが並び、燈籠が連なる。先方に簡素な門形をした門がある。其の門が奥院の境内を現すのである。
正面に小さな奥院がある。左手に船形石が石垣に嵌め込まれ、右方の簡素な社務所には、手持無沙汰に作務衣の作男が、境内を歩く男女を眺めていた。
平坦な境内のせいか、殺風景で空間に主要なポイントがなく、ポイントを取り巻く要素、点景も、恋の道の終着駅にしては物足らぬ印象である。
本殿裏に天然記念物の桂の木があると聴いていた。一度川沿いの道に出て進むが、奥院より先は、林内の手入れもされておらず、荒れた印象だ。雑然とした林内に天然記念物の桂の木が立つが、桂の木を取り巻く状況に―気―は感じられなかった。
恋の道の帰り掛けに、山側の石垣上に閑静な佇の料理屋があった。石垣の積まれた崖は相当に高く、苔生して風情がある。L形に折れた石垣と石垣の間に頂に登る石段が伸びる。頂にある店は肌理細かなデザインがなされ、暫し佇み見蕩れた程だ。
貴船川沿いの道を降る。バス停近くの湧水で口を漱(すす)ぐ。冷たく気持がいい。バス停で待つ探索者もいるが、歩いて川沿いを貴船口駅に向かう。左手には貴船川に萌黄色の若葉が差し掛かり、右方には山の斜面が連なる。
変化のある光景だが、疲れのせいか、無表情に只管歩く。行き交う人もそれ程なく、前を進むカップルも、只管無表情に歩く。彼等とどちらが先に貴船口駅に着くか競争しているような気持で歩いていた。
三十分程で小さな貴船口駅に着く。狭い石段を数段上がった処が駅だ。川沿いを行き交う探索者は少なかったが、駅には数人電車の到着を立って待っていた。
登山に比べたら、それ程歩いていないが、コンクリートの道を歩いたせいか疲れた。
疲れた体で、車窓に流れては消え、再び現れて流れる風景を、ボンヤリと眺める。眠気に襲われたが、流れ去る穏やかな田園風景に瞼を閉じるのは勿体無いような気持である。
宝ヶ池駅近くでは左方に、比叡山の山稜が夕暮の穏やかな陽を受け、淡い輝きを照り返していた。なんと長閑な風景だろう・・・。
|
Copyright(C) Sousekei All rights reserved.