

|
| サイトリスト | ||||
|
古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |
京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリアの町並 アフガニスタンの町並 |
| 8 赤山禅院から修学院離宮へ | 8 赤山禅院から修学院離宮へ-スケッチギャラリーへ | おすすめサイト | ||||||
 |
 |
|
||||||
| 赤山禅院山門 | 赤山禅院 | |||||||
 |
 |
|||||||
| 赤山禅院 | 修学院離宮上の宮隣雲亭 | |||||||
| 京都インデックス | ||||||||
|
||||||||
| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||
| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |
||||||||
|
八 赤山禅院から修学院離宮へ
白川通りも詩仙堂近くになれば、静かな佇の道だ。修学院道で下車しようとバスを降り掛けた。運転手が修学院離宮道は次だと云った。直に次の修学院離宮道に着いた。私は車窓の景色をぼんやりと眺めていた。私の席は運転手近くの斜め後方だ。
「修学院離宮道で、降りるんじゃないんですか」
そう運転手は声を掛けて来た。降りる乗客はいない。親切な運転手で、降車ボタンを押してもいないのに、停まって呉れたのである。
音羽川沿いのアスファルト道路を上る。午前中だが、九月の陽差しはまだ強い。赤山禅院と修学院離宮に別れる角に出た。真直に伸びた道の突き当たりに、修学院離宮の総門が見えた。門前の前庭に三人の人影があった。修学院離宮参観の人だろう。参観の時刻は十一時の筈だが、随分早く来ている人もいるものだ。
角を左方に折れれ、二三の商店が並ぶ道を進んだ。右手に大きな石鳥居が見えた。鳥居の中央に少し傾げて大きな額が掛けられー赤山明神ーとあった。鳥居の先方には、両側を木立ちに包まれた、上り坂の参道が伸びる。見上げる程の大きな鳥居の横に伸びた桁の少し上に、比叡山の山並が、薄紫色に霞み、穏やかな稜線を描いていた。
坂道の参道の左方に、土塀が連なる民家があった。連なる土塀を穿って閑雅な門が立ち、邸内からは、庭に立ち上がる樹木の枝葉が塀に差し掛かり、枝葉の葉擦れに古風な母屋が覗く。
参道は幾らか細くなって総門を抜け、左方に緩い弧を描き、緑葉に吸い込まれてゆく。総門両脇は、幾層にも織り重なった緑葉に包まれ、門の中央部のみ現れるに過ぎない。全てが見えないだけに、趣きがある。総門は黒々とし、古色蒼然とした佇だ。右手の柱にはー天台宗修験道総本山管領所ーとあった。一昨年秋たけなわの頃、赤山禅院を訪れた。紅、橙、黄色に彩られた枝葉が、総門から伸びた参道に差し伸べられ、陽光を受けた紅葉の葉裏は、透き通るような鮮かさであった。その時の賑わいが嘘のように静かな参道である。
緩い坂道の参道を登り詰めた処に、簡易な屋根を差し掛けたただけの茶店があった。左方の石段との間には、縁台の長椅子が置かれてあった。
石段両脇に立ち上がる樹木の差し掛ける枝葉の葉擦れに、赤山禅院本堂の大屋根が葺き降るのが垣間見える。本堂の左手前には、売店兼用の受付が立つ。石段を上がった両脇にはー赤山明神ーと銘の入った提灯が、立ち上がった細い柱から持出され浮かんでいた。空間の装置として提灯は、好い点景だ。
秋に訪れた時、茶店の前で、地元の婦人会の女性達が、抹茶の接待をしていた。素晴らしい紅葉を愛でながら、茶を喫(の)んだのを思い出した。その時この辺で、骨董市が開かれ、私も清水焼の小皿を十枚買った。
秋、錦秋につつまれた本堂、今は、緑葉に包まれ落着いた佇だ。本堂脇から境内裏手を回る。境内には、小さな堂が幾つか立つ。その他に、小祠が彼方此方(あっちこっち)に散らばっている。それぞれの祠にはひとつひとつ御利益があるらしい。
順路に従い進む。本堂裏手の寛老池の畔に、鬼蜻蜒(おにやんま)の飛ぶ姿があった。思わず、はっとした。鬼蜻蜒は境内の散策路を音も無く滑るように飛んで行った。鬼蜻蜒は、同じ道を行ったり来たりする習性がある。
飛び去って行った鬼蜻蜒は、又来た道を戻って来た。気のせいか、八ヶ岳山麓に飛ぶ鬼蜻蜒より図体が大きく感じられた。小さな池もあったりして、鬼蜻蜒の生息にとって恰好な環境だ。
境内の外縁は、鬱蒼とした林に包まれ、足は踏み入れられない。林に切れ込んで、筋の長い石段が上方に伸びる。途中、石段が僅かに右方に折れた処には、石灯籠が据えられ、頂に小さな社が覗いていた。林に切れ込んだ石段であるため、両脇には、幾本か樹木が立ち上がり、幽暗な空間を現していた。
池があり樹木が繁っているとなれば、当然、藪蚊が沢山いる。スケッチをする間にも、何ケ処か刺された。払い退けても直に別動隊が、特攻隊の如く飛び込んでくるのである。
石段を上がり切った処では、右方に道が伸び、小さな社が三つ四つ並んでいた。私の後ろから上がってきた夫婦は、社の一つ一つに掌を合わせ、経を唱える。一つ終われば直に次へ移る。信仰心が篤いわりには。忙しそうな主人だ。
赤山禅院の境内は狭い。一周して受付に戻った。受付でお札に印形を押していた人に訊いた。
「赤山禅院では、住職さん不在で、婦人会の人達が寺の運営をしているんですか」
秋に訪れた時、そのようなことを聴いた覚えがあった。現に、その時婦人会の女性達が、寛老池の畔で縁台を据え甘酒や茶、抹茶の接待をしていたのであった。
「いえ、其んな事はありまへん。住職さんはいてはります。婦人会と事務の我々は別です」
受付の中で忙しそうに手を動かしながら、女性はそう云った。
赤山禅院は、皇城の地、京都の表鬼門に位置し、赤山明神(陰陽道の(おんみょうどう)祖神・泰山府君(たいざんふくん))を皇城の鎮守として祭祀する比叡山延暦寺の別院である。
来た道を戻って石鳥居を潜り、修学院離宮へ向かった。遠くから、総門前に集合する人達が見えた。まだ十一時までには、十分程間がある。総門近くに閑静な路地があった。素早く板塀の連なる路地のスケッチを始めた。戻って、総門前に眼をやった。既に待つ人は誰もいない。急いで修学院離宮の総門に進む。門脇には携帯電話を腰に付けた門衛が立つ。
私は無言で、離宮の総門に足を踏み入れた。擦れ違った時、門衛に呼び止められ、
「参観許可証は・・・」
昨日、宮内庁京都事務所で渡された参観許可証を、ウエストポーチから取り出し、門衛に提示した。
「右手奥の休憩所で待っていて下さい」
門衛は振り返って、そう云いながら、林の奥方に手を向けた。
林の中に立つ休憩所には、数人の参観者が、修学院離宮を映したビデオを見ていた。外国人が二人、青年が三人、あとは中年以上の男女だ。若者は建築学科の学生だろうか、などと勝手に思った。私も学生時代、友人の共に修学院離宮を訪れたことがあったから。
私も暫くビデオを見ていたが、折角、実像の修学院の佇が眼前にあるのだから、そう思って外の緑豊かな自然に眼をやった。
定刻十一時、背が高く、穏やかな動作の男が、休憩所の硝子戸の外で、
「それでは、これから参観に行きます・・・」
緩っくりとした口調で男は話した。男の腰には、色々な鍵のついた束がぶら下がっていた。参観者は、男の後ろに従(つ)いて、砂利道を進んで行った。
砂利道が広がった処に面し、屋根が差しかかった木製の薄っぺらい戸が立つ。戸の両脇には、板塀が連なり、それに続く緑葉に溶け込んでゆく。男は腰にぶら下げた鍵の束を、手に持ち替え、木戸の鍵穴に差し込んだ。戸を押し開けた男に続き中に足を踏み入れた。
まずはー下御茶屋ーである。庭園内の道を男に従いて進む。下御茶屋・寿月観(じゅげつかん)は、現在、屋根の柿葺の葺き替え中で、足場が掛けられて白いシートで蔽われ、隙間から垣間見れる程度だ。
柿葺は(こけらぶき)、十年に一度、吹き替えねばならない。寿月観を回り込んで庭園を上る。けれども庭園に付けられた石段は、薄っぺらな戸に突き合ったってしまった。私が先頭だった。
「門があるから、戻らねばならないようだ」
そう云って、私は戻り掛けたところへ、鍵の束を手に男が緩っくりと上がって来た。木戸を押し開け、男は先に進んだ。我々は男に従いて行った。
修学院離宮では、一つ一つの園地に木戸が設えられている。警備上、そうしているのであろう。
畑の中に築かれた道を進む。右手遙か彼方に京都市街が霞み、西山の山並が薄紫色に棚引いていた。道脇に立ち上がる松並木から、それらが小さく見渡せる。
此の畑の中に付けられた道は、既にかなり高い位置にある。道は周りの畑より高く築かれ、下方の畑では、農夫が二人、畑仕事をしていた。なんとも長閑な風景で、田舎の棚田の畦道を歩いているような錯覚を憶えた。道の左手には、更に広い畑が拡がる。刈り入れの終わった稲束が、棚田に掛け渡された丸太に、逆さに下げられている。それらが黄金色の小さな壁のように、疎らな間隔で棚田の中にあった。
棚田では、地形に沿って、畑が幾段も横筋を引き、一面に平坦に畑地があるのとは異なり、肌理細かい印象を受ける。
背には比叡山の山並が、なだらかな稜線を引いて藍青色の空に、優しい姿で現れる。これだけをとれば、とても、私が今いる処が、修学院離宮であるとは思えない。既成の先入観念からすれば、そう感ずるのも無理はない。
けれども、そう云った広々とした田園風景の中に、下御茶屋、中御茶屋、上御茶屋を分散して配置したのが修学院離宮の特徴なのである。
この畑地は、後水尾上皇の時代には、離宮の一部だった。それが、いつの時代からか、近隣の農夫が畑地として使い出し、所有権は彼等のものになった。明治時代に、それらの畑地を宮内庁が買取り、離宮の敷地とした。近郊の農民には、今まで通り畑地を使うことを許可した上で。収穫した農産物も彼等に帰属する条件らしい。
そんな話を、案内人の男から聴いた。我々参観者は、門衛の立つ厳(いか)めしい門から離宮に入ったが、棚田で畑仕事をする農夫達には、別の入口があるのだろうか。そんなことを話を聴いて、ふっと脳裡を過(よぎ)った。
道の突き当たりにある中御茶屋の戸を、案内人の男は、例の鍵の束を手にもって開けた。濃紺のスーツに身を包んだ男は、相変わらず、静かに足を進め、物言いも穏やかである。場合によっては慇懃無礼(いんぎんぶれい)な態度と感ずる時もあるかも知れない。公家の末裔の匂いがないとも云えなくない。生気が抜け、形式のみが表に出、蝉の抜殻のような印象だ。
先頭を歩く男と共に、参観者の列の最後尾にも、若い男が従いて来る。若い男は、こちらから話し掛けなければ、口を開くことはない。参観者が間違いなく、参観した茶屋を退出したのを確認した上、腰にぶら下げた鍵の束を手に取って、鍵穴に差し込んでいた。
私は処々で、速描きにスケッチをする。私が描き終わる迄、若い殿の(しんがり)男は、無言で私の背に立って待つ。速く描けといわれているような気持だ。二言三言、話しても罰は当たらないだろうに、無言で立っていた。
そんな訳で、スケッチも落着いて出来ない。宮内庁の職員ともなれば、職務には関係ないことは、述べてはいけないのだろうか。
殿の若い男は、体格がいゝ。後日、参観した桂離宮では、この案内役の男達は皇宮警察官だ
と云っていた。多分、修学院離宮の案内人も、そうに違いない。私が不審な行動を起こそうものならば、すかさず、頑健な体にものを云わせ、組み伏せにかゝるに違いない。
私を除いた参観者の列の最後尾は、先の方にいってしまった。殿の男に注意される前に、素早く描き上げ、列の背を追いかけた。
再び板戸を潜り抜け、畑の中を抜けた道を進む。右前方に、上御茶屋の堰堤(えんてい)の大刈込みが横筋を幾段か引き陰影を現す。堤には樹林が幾本か立ち上がる。緑葉に包まれた枝葉は、左手の林に溶け込んでゆく。
右手の丘の頂に、上御茶屋の隣雲亭(りんうんてい)が豆粒のように小さく見える。こうして見るに、上御茶屋は、かなり高処にある。さぞかし見晴らしは素晴らしい眺めであろう。
公家風案内人そして殿の男に気をとられ中御茶屋について述べることを忘れた。中御茶屋は、歴史の途中から林丘寺(りんきゅうじ)の境内に組み入れられた。其処には楽只軒(らくしけん)と客殿が立つ。
林丘寺の境内に立つ、楽只軒と客殿は宮内庁に、明治十九年返された。林丘寺は背後の丘に移ったのである。楽只軒は簡素な茶屋である。客殿の床の間の壁が、現代的デザインで面白い。
床の間は本床(ほんどこ)で畳が敷かれてある。四十センチメートル程の高さ迄、紺色をした和紙が千鳥に貼られ、一本、横に帯を流し、上部は斑な壁になり、中段上部には、金箔が互い違いに貼ってある。桂離宮にも見られる大胆なデザインだ。恰もモンドリアンの絵画を思わせる。
客殿床の間に進んで、一間半の横幅で霞棚が(かすみだな)ある。棚が連続的に右上がりにつけられ、下部は地袋である。桂離宮の桂棚、醍醐寺三宝院の醍醐棚と共に天下の三棚と呼ばれる霞棚だ。
畑の中の来た道を進む。三差路を右方に折れ、松並木を緩っくりと登る。松の樹幹越しに、右手には、棚田が末広がりに降っている。左方の畑の向こうに、浴龍池(よくりゅうち)の堰堤大川込みが徐々に、大きく現れて来た。
上御茶屋への入口にも板戸があった。私は最後尾だったため、入口に着いた時には、既に板戸は開かれ、列の先頭は先の階段を上がっていた。上御茶屋隣雲亭に至る細い石段は最後の上りだ。石段の両脇は綺麗に刈り込まれた灌木で埋め尽くされていた。
上りながら、横に眼をやった。円く刈り込まれた灌木が葺き降った先に、浴龍池の水面が見渡せる。
隣雲亭前庭で、案内人の男は、
「此処で、少し休憩します」
少しとは十分なのか、五分なのか定かではない。浴龍池を見下ろし、スケッチすることにした。と云うより、直に描き始めたのである。
浴龍池は自然な曲線を描く。西浜の堤には、樹木が等間隔に立ち上がり、其処に道がつけられているのが分かる。堰堤の大刈込みの灌木が堤に頭を覗かせる。池の上方へは緑葉が緩く這い上がり、比叡の山並へと連なる。緑葉の遙か下方には黄金色の畑が覗く。
遙か彼方の遠方には、京都市街が蜃気楼の如く見え、その向こうには、嵐山、西山の山並が薄紫色に霞んでいる。遠景、中景、近景どの空間要素をとっても、素晴らしい眺めだ。それらの一つでも欠ければ、全体の空間系の素晴らしさは失われるだろう。筆を走らせるのが、精一杯で、とても色付けする時間的な余裕はない。
|
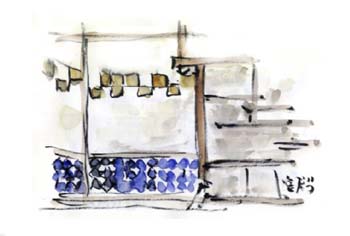 |
 |
| 修学院離宮客殿 | 修学院離宮中の宮 |
| 描きながら考えた。桂離宮の庭園は、主屋の書院の前面に拡がる園地に対し、松琴亭、賞花亭、笑意軒の各茶屋が、程よい距離を保って計画され、それぞれが空間的に認識できる。それは離宮が立つ立地条件にもよるのだろうが・・・。桂離宮は飛躍せずに、一つの空間系として知覚できる。
一方、修学院離宮においては、一つの空間系として知覚するには、下御茶屋、中御茶屋、上御茶屋の各茶屋それぞれが、独立性を持って立つ。修学院では、桂の書院に相当するであろう、中心的建築は考えられていない。
もともと修学院では、中心的空間は必要としていないかったとも云えるのではないだろうか。それに替わり、修学院は広々とした田園を内部に持つ。
修学院離宮をつくった後水尾上皇は、江戸幕府と対立し、幕府との軋轢(あつれき)によって、現実の世界から逃れ、自らの胎内で完結する世界を、つくり上げたのではなかろうか。
後水尾上皇は修学院離宮、その中に完結した生活、社会を表現したのではなかろうか。上皇は表現された空間で、自らの小宇宙を創り上げ、書画を始めとした芸術を謳い上げって行った。
上皇は離宮の中では、幕府との軋轢を離れ自由に振る舞える。畑あり池あり林あり、思いつく自然の自由が鏤め(ちりば)られている。一つだけないものがある。庶民の自由と労働だ。
併し、自由と労働がないとは云え、上皇は、究極的には、それを求め、それに限りなく近付くために修学院離宮を、造営したに違いない。
上御茶屋、隣雲亭での休憩もそうながくはない。素早く描けそうな突き出し窓をスケッチした。座敷の窓に嵌められた板戸が、一本の棒で突き出され、窓の下方だけが、外部に開かれる。
開かれた部分から明るい陽光が差し込み、室内の仄暗さとは対照的に、其処からは、燦々(さんさん)と陽を受け、輝く緑葉と、彼方の西山の山並が薄紫色に霞むのが、敷居と板戸で構成された額縁の中に見えた。
上御茶屋は、修学院離宮の中では、クライマックスの空間だ。緩っくりとスケッチをしながら過ごしたいとところだが、参観時間は全てで一時間足らず、既に戻る刻のようだ。
隣雲亭を後に浴龍池へと降る。浴龍池に浮かぶ二つの島に掛け渡された、中国風の千歳橋が、立ち上がる木立ちの枝葉の葉擦れに見えて来た。千歳橋の基部は切石で積み上げられ、西側の島に四阿風(あずまや)の方形の屋根がのせられていた。千歳橋は、修学離宮の中では異質の空間だ。日本建築特有の曖昧さがなく、橋と云う機能が明確に打ち出されている。
浴龍池の堰堤、西浜に足を踏み入れる。先刻まで参観していた隣雲亭が緑葉に包まれ、豆粒の如く、山の中腹に浮かぶ姿があった。
西浜の西側には大刈込みが築かれ、遙かに京都市街が見渡せた筈であった。けれども、上方の隣雲亭に気をとられて許りいた。
来た道を戻る。殆どの参観者は休憩所に再び行った。私は門前で暫く休んでいた。
修学院離宮の南に鷺森神(さぎもり)社がある。修学院離宮と曼殊院に挟まれ、観光スポットには遠い存在だ。けれども、静かで落着いた神社、特に秋の紅葉は素晴らしい、と聴いていた。鷺森神社に寄り、その後、時間が許せば深泥池(みどろがいけ)の円通寺を訪ねたい。修学院離宮から山麓の道沿いを曼殊院方面に足を進めた。その途中に、鷺森神社はある。
幾つかの角を折れるうちに、自分がどの辺にいるのか分からなくなった。近在の人に訊く、
「其処を下がった処の左の方に鷺森神社はありますよ」
教えられた通りに、人家が立ち並ぶ道を行くが、なかなか鳥居が見えて来ない。かなり歩いてから、左方に鳥居が見えた。石の鳥居からは、真直に坂道の参道が伸びる。石畳の参道沿いには、家が並び、参道を道路としても利用している風だ。明らかに建築基準上道路と認定されている。と云うより、法律が出来るずっと前から、参道沿いには家が建っていたと思われる。そんな訳で、参道は自動的に建築基準法上の道路と認定されているのに違いない。
少々、疲れ気味だ。真直に伸びた坂道の参道を前に、鷺森神社に行くかどうか迷い、一度、戻り掛けた。頭の片隅に円通寺が浮かぶ。そして再び、参道に足を踏み入れた。
石畳の参道の両側には、樹々が立ち上がり、その枝葉を参道に差し掛け、参道は緑葉のトンネルだ。上方から涼しい風が吹き抜けて来る。参道を上がり切った処に、案内板が立つ。左方に抜ける脇参道が、横に走っていた。そこには、陽差しが差し込み、きらきら輝いていた。煌めく先に、小さな石鳥居が立っていた。
この鳥居を潜れば近かったたのに・・・。私は、鳥居を見過ごしてしまった。小さな鳥居は、人家の連なりの一部にあったので。
鷺森神社の境内には、近在に住む人が、時折、抜け道として通り過ぎて行く位で、流石に此処までは探索者は来ない。静寂に包まれた境内だ。ただ一人だけ、東京から来たと云う若い女がいた。その人も直に、曼殊院への道を林の方に消えて行った。
鷺森神社の境内に立つ建物は、社殿の周りにまとまってある。社務所を過ぎ、上家の架かった手水鉢、吹晒しになった能舞台の前の石段を上がった処に唐破風の社殿が立つ。社殿を中心にした構図で、スケッチを始めた。境内のレベルより一・五メートルほど高い処に社殿は、静かに佇む。
社殿の背には、樹々が織り重なる。緑葉の葉擦れに樹幹が幾本も現れ、薄茶色をした社殿とよく響き合う。描く間に、私の背の林の中から、幾人かの近在の人が現れては、参道の方に消えて行った。無言で、眼が合えば、軽く黙礼する程度である。風に戦(そよ)ぐ音などは聴こえる訳がないが、静寂に包まれた境内では、眼前にある光景が、音曲を奏でているように感じられる。
もう一つの参道、小径に曼殊院方向を示す矢印があった。描き終え、標識に誘われるように、小径に足を踏み入れ、鬱蒼とした林の中に分け入っていた。
足を踏み入れて二三歩、左方の林に石段が伸び、途中から消え入るように林に吸い込まれて行った。石段の両脇には、自然な形の土手が林内に繋がっている。ありふれた林内の小径には違いないけれども、人工物である石段が、さりげなく自然の胎内に入り込み、見事な空間をつくり出していた。
奥床しい石段に魅せられ、石段に足を進めた。石段を上がった処に、小さな祠があった。辺は、いくらか踏み固められ、自然に林内へと入ってゆく。先方には、小暗い林が続き、其方には小径はつけられていない。
上がってきた石段に戻る。もう一本の小径は、近在の人の抜け道になっているようだ。買物に行く年配の人と時々、擦れ違う。
林を抜けた辺に、小さな橋が差し掛けられていた。橋を渡って、径は右方に折れ曲がり、緩い坂道となって、曼殊院に至るアスファルトの坂道に出た。昔は、アスファルト道路は、石畳の参道だったと思われる。その頃には、このスロープはなく、石畳の参道に、平らに交差していたのであろう。けれども、この坂道は、如何にも生活の匂いを感じさせ、思わず顔が綻ん(ほころ)でくる。まず、近在の人だけしかこの道が何処に至るのかは分からないであろう。
鷺森神社で思いのほか刻をついやした。これから円通寺を訪れても、緩っくり出来そうもない。シドニーオリンピックサッカー、日本対ブラジル戦、六時にキックオフだ。今日は祇園のギャラリーに寄って、早めに帰ることにした。
最近は歳のせいか、疲れ易い。白川通に出、一乗寺清水町から京都駅行バスに乗り込んだ。四条河原町までは、十五分ほどだったが、つい微睡(まどろ)んでしまった。
四条通を八坂神社方面に進んだ左方に俵屋画廊はある。一階は喫茶店で、その中に画廊が併設されているのでは、そう思って、ウインドー越しに店内を覗いた。
画廊は二階だった。狭い階段を上がって行った。突き当たりの枠に嵌められ、ぴかぴかに磨かれた硝子戸を押し開ける。細長い壁面に値段が高そうな絵が、ぶら下がっていた。展示された絵を見ると、俵屋画廊は貸画廊ではなく、企画画廊あるいは、画商の本拠地としてのショールーム画廊のようだ。
画廊に足を踏み入れ、二三分で、階段をこつこつと、上がっ来る靴音が聴こえた。硝子戸を押し開ける「シュー」と、風を切る音が聴こえ、背を振り返った。白のブレザーを着込んだ男が立っていた。私と眼が合い、互いに軽く頭を下げた。画廊の主人だ。
早川紀久忠の果物を描いた水彩画は、色が鮮かで上手な絵だ。十号位の大きさで三百五十万円だそうだ。
「三百五十万とは、今ではいゝ値段ですね」
「ええ、作家の遺族の方が、その値段であれば売ってもいいと云ってるもので・・・。別段、生活に困る人でもないので・・・」
主人の松本さんはそう云った。斉藤逸郎の絵は、鉛筆で克明に描いた抽象画だ。気が狂いそうなぐらい細かく、面白い絵だ。松本さんは私が色々と訊ねると、親切に教えて呉れた。前以て、私のところも、東京吉祥寺の営業所が一部、画廊になっていることは話しておいたからか。
そのうちに、奧のテーブルに座るように、手を向けられた。
「娘が関西大学に行っているので、時々、京都、奈良を絵を描きながら探索しています。紀行文風に文章も書いています。来年あたり、京都で、紀行文の原画展をしようと・・・」
「京都では、そう云った展覧会は、よくあります。それだけに新しさがなく、却って東京新宿のビル街とか、ゴールデン街を描いて、京都で個展を開いた方がよいのでは・・・」
京都の人は、いゝものに対しては、遠く迄でかけて見に行く。自分の身の回りには、文化的
レベルの高いものが沢山ある。どうでもいゝものを見に、わざわざ外にでかけない。そう松本
さんは云っていた。
食いだおれの大阪 大阪には倉庫が沢山あり、杭にのっているものもあった。それが今で は殆どなくなっているの意
着だおれの京都 京都人は、気位が高く、かつ気が強く、結果的に身をもち崩す意
履きだおれの神戸 六甲の風で枯葉が舞い散らかり、それを掃くのが大変の意
なんで、そんな話になったのかは忘れたが・・・
主人は博学な人だ。
「最近、絵は売れてますか。銀座あたりでもそれ程、売れているようには思えませんが」
「私のところは、一度、価値のある絵を世話して、買って貰った人は、二三年の間には、又買って呉れますよ」
関東と関西の文化の比較、人間の考え方の違いなどについて、互いの持論を述べ合った。松本さんは画廊のオーナーだけに、文化、人間を、経済的論理で構築しがちであった。
「サッカー、ブラジル戦は大丈夫ですかね」
「うーまあ・・・」
最後は、経済的論理から逸れた、サッカー日本対ブラジル戦で締め括り、俵屋画廊を後にした。
|
Copyright(C) Sousekei All rights reserved.